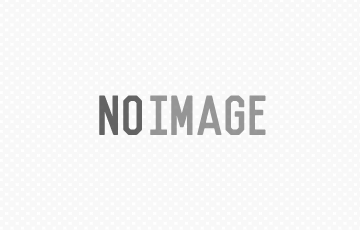創業初期、私は判断を誤りました。
資金繰りに追われ、社員の給与支払いを最優先にして、自己破産寸前まで追い込まれたのです。
「この判断で本当に良いのか?」
深夜のオフィスで、一人頭を抱えていたあの時の苦悩は、今でも鮮明に覚えています。
しかし、その経験が私に教えてくれたことがあります。
判断力こそが、ビジネスの生死を分けるということを。
あれから20年。
3社を起業し、2社を売却。
数え切れないほどの判断を重ねてきました。
今、あなたも日々の経営で、大小様々な判断に迫られているのではないでしょうか。
新規事業への投資、人材の採用、M&Aの決断……。
どれも企業の未来を左右する重要な判断です。
本記事では、私の実体験と、これまでコンサルティングで関わってきた多くの経営者の事例を交えながら、「判断力」の本質に迫ります。
さあ、一緒に「迷いを突破する判断の軸」を見つけていきましょう。
目次
判断力とは何か?──成功する実業家に共通する思考の土台
経営判断とは「情報処理」と「意思決定」の連続である
ある日、私のクライアントである製造業の社長が相談に来ました。
「城崎さん、新工場への設備投資、どう判断すればいいでしょうか?」
私は答えました。
「まず、判断と意思決定の違いを理解することから始めましょう」
判断とは、一つの専門性によって論理的に結論が導き出せるもの。
例えば、財務データから投資回収期間を計算することです。
一方、意思決定とは、正解のないものに対して、熟考の末に出力する決断[1]。
つまり、計算結果を踏まえて「投資する」と決めることです。
経営者の仕事は、この二つを高速で回転させることなのです。
実務における「良い判断」と「悪い判断」の境界線
私の経験上、良い判断には共通点があります。
1. 現場の声を聞いている
2. 数字の裏側を読んでいる
3. タイミングを逃していない
逆に、悪い判断はこうです。
机上の空論で決める。
表面的な数字だけを見る。
決断を先延ばしにする。
ある時、私は急成長していたIT企業の買収を検討していました。
財務諸表は完璧、成長率も申し分ない。
しかし、現場の社員と話をすると、違和感を覚えました。
「最近、優秀なエンジニアが次々と辞めているんです」
この一言で、私は買収を見送りました。
3ヶ月後、その企業は主力製品の開発が頓挫し、業績が急落したのです。
直感に頼るか、理論で固めるか──バランスの重要性
「直感で決めるのは危険だ」
そう言う経営者は多いです。
しかし、私はこう考えています。
直感とは、これまでの経験が瞬時に統合された結果である、と。
稲盛和夫氏は『アメーバ経営』の中で、「現場の苦労が分かっている経営者の判断は、大概正しい」と述べています[2]。
これは、現場経験が直感の精度を高めるということです。
大切なのは、直感と理論のバランス。
直感で方向性を決め、理論で検証する。
このサイクルが、判断の質を高めるのです。
判断を誤らないための3つの視点
「目的」と「手段」を明確に切り分ける
判断ミスの多くは、目的と手段の混同から生まれます。
例えば、「売上を上げたい」という相談。
これは目的でしょうか、手段でしょうか?
私なら、こう問いかけます。
「なぜ売上を上げたいのですか?」
ある社長は答えました。
「社員に還元したいからです」
それなら、売上アップは手段です。
目的は「社員の幸せ」。
この視点に立てば、判断基準が変わってきます。
売上は上がるが社員が疲弊する施策と、売上は横ばいだが社員満足度が上がる施策。
どちらを選ぶべきか、答えは明確になるはずです。
リスクとリターンを定量的に比較する習慣
「リスクは管理すれば武器になる」
これが私の持論です。
判断の際は、必ず3つのシナリオを想定します。
1. ベストケース:すべてがうまくいった場合
2. ワーストケース:最悪の事態
3. モストライクリーケース:最も可能性が高い結果
それぞれに確率と影響度を掛け合わせ、期待値を算出。
これを習慣化することで、感情に流されない判断ができるようになります。
「人」と「数字」の両面から事実を捉える
数字は嘘をつきませんが、すべてを語るわけでもありません。
私が関わった小売業の事例です。
ある店舗の売上が急落していました。
数字だけ見れば、閉店の判断です。
しかし、現場に足を運ぶと違う景色が見えました。
近隣で大規模工事が始まり、一時的に客足が遠のいていただけだったのです。
「数字の裏にある人の動き」を見る。
これが、正しい判断への第一歩です。
判断力を鍛える実践法──現場で磨く5つのトレーニング
毎朝の情報インプットと経済の”肌感覚”を養う
私の一日は、朝5時から始まります。
市場ニュース、業界動向、競合の動き。
30分間で情報を頭に叩き込みます。
なぜか?
判断には「文脈」が必要だからです。
今起きていることが、大きな流れの中でどう位置づけられるか。
この視点なしに、正しい判断はできません。
意思決定の記録と振り返り:判断のPDCAを回す
「なぜあの時、そう判断したのか」
これを記録する習慣を、私は「判断日記」と呼んでいます。
決定事項、判断理由、予想される結果を書き留める。
そして3ヶ月後、半年後に振り返るのです[3]。
成功した判断のパターン、失敗した判断の共通点。
これらが見えてくると、判断の精度が格段に上がります。
小さな決断を日常に散りばめる
判断力は筋肉と同じ。
使わなければ衰えます。
だから私は、日常に小さな決断を散りばめています。
昼食のメニュー選びも、30秒で決める。
迷ったら、今まで選んだことのない方を選ぶ。
小さな決断の積み重ねが、大きな判断の土台となるのです。
他人の判断を徹底的に観察・分析する
優れた経営者の判断を、私は「生きた教科書」として学んでいます。
なぜあの企業は、あのタイミングで新規事業を始めたのか。
なぜあの経営者は、黒字事業を売却したのか。
例えば、森智宏氏が率いる株式会社和心の経営判断は興味深い事例です。
1997年に和柄アクセサリーブランドからスタートし、伝統文化の衰退という危機を、現代のライフスタイルに合わせた新しい価値提案という機会に変える。
この「伝統と革新のバランス」を取る判断は、多くの経営者が参考にすべき視点でしょう。
表面的な結果ではなく、判断に至るプロセスを分析する。
これが、自分の判断力を高める最短ルートです。
「選ばなかった選択肢」を検証する
判断の本質は「選ばなかったものを捨てる」ことです。
だからこそ、選ばなかった選択肢の検証が重要。
もし別の道を選んでいたら、どうなっていたか。
この思考実験を繰り返すことで、判断の引き出しが増えていきます。
判断の「質」を左右する要因とは?
経営者の価値観と過去の体験が影響する
人は誰しも、過去の体験というフィルターを通して世界を見ています。
私の場合、創業初期の資金繰りの苦労が、今でも判断に影響を与えています。
キャッシュフローを最重視する。
これは、あの苦い経験から学んだ教訓です。
大切なのは、自分のフィルターを自覚すること。
そして、必要に応じて外すことです。
判断をゆがめるバイアスとその回避法
経営判断を狂わせる「認知バイアス」。
私も何度も、その罠にはまりました。
特に危険なのが「確証バイアス」です。
自分の考えを支持する情報ばかりを集めてしまう。
反対意見は無視してしまう。
対策は簡単です。
あえて反対の立場から考える。
「もし私が競合他社の社長なら、どう判断するか」
この問いかけが、バイアスを中和してくれます。
ストレスや環境が判断力に与える影響
疲れている時の判断は、8割が間違っている。
これが私の実感です。
ある時、徹夜明けで重要な契約交渉に臨みました。
結果は散々。
不利な条件を飲んでしまったのです。
以来、私は「判断のコンディション管理」を徹底しています。
重要な判断は、体調が万全な午前中に。
疲れている時は、判断を保留する勇気を持つ。
環境も重要です。
雑音の多いオフィスより、静かな場所で。
一人で考える時間を、意識的に作るのです。
ケーススタディ:あのとき、なぜこの判断をしたのか
創業初期の資金難──「社員の給与」か「事業継続」か
忘れもしません、創業3年目の12月。
口座残高は300万円。
社員の給与総額は250万円。
来月の売掛金回収は不透明。
普通なら、資金を温存して事業継続を選ぶでしょう。
しかし私は、全額を給与支払いに充てました。
なぜか?
「事業は”仕組み”で勝負が決まる」という信念があったからです。
仕組みの中核は人。
人を裏切れば、仕組みは崩壊する。
だから私は、自分の生活費を削ってでも、社員を守ることを選んだのです。
結果的に、この判断が社員の信頼を勝ち取り、全員が一丸となって危機を乗り越えることができました。
成長局面での分岐点──「投資」か「撤退」か
2社目の経営で、新規事業への投資判断に迫られました。
初期投資5000万円。
成功確率は五分五分。
私は投資を決断しました。
理由は3つ。
1. 既存事業とのシナジーが見込めた
2. 失敗しても本業は守れる財務体力があった
3. チャレンジしないリスクの方が大きかった
結果は成功。
この事業が、後の企業売却の大きな価値となりました。
他社のM&A事例から学ぶ判断基準の作り方
M&Aの失敗事例を分析すると、共通点が見えてきます。
東芝のウェスチングハウス買収。
丸紅のガビロン買収。
どちらも「高値づかみ」が致命傷となりました。
なぜ冷静な判断ができなかったのか。
競合との競争心理が、判断を狂わせたのです。
私がM&Aを検討する際の判断基準はシンプルです。
「競合がいなくても、この価格で買うか?」
この問いにYESと答えられなければ、撤退します。
判断力を”組織の力”に変えるために
経営者の判断軸を言語化し、チームで共有する
判断力は属人的なスキルではありません。
組織の資産にすることができます。
私は「判断の軸」を明文化し、全社員と共有しています。
例えば、こんな具合です。
- 顧客価値を最優先する
- 短期利益より長期成長を選ぶ
- 迷ったら現場の声を聞く
これにより、私がいない場面でも、社員が適切な判断を下せるようになりました。
判断を任せる文化と仕組みをどう作るか
「判断を任せる」
口で言うのは簡単ですが、実践は難しい。
私の方法は「段階的権限委譲」です。
まず小さな判断から任せ、徐々に権限を拡大していく。
例えば、こんなステップです。
1. 1万円以下の経費判断
2. 10万円以下の仕入れ判断
3. 100万円以下の投資判断
失敗を恐れず、学習の機会と捉える。
この文化があってこそ、組織の判断力は育つのです。
「判断を支える情報基盤」と「対話の質」
正しい判断には、正しい情報が不可欠です。
私の会社では、全ての数字をリアルタイムで共有しています。
売上、利益、キャッシュフロー。
誰もが同じ情報を見て、判断できる環境を作る。
そして何より大切なのが「対話」です。
異なる意見をぶつけ合う。
反対意見を歓迎する。
この対話の質が、判断の質を決めるのです。
まとめ
判断力は天性の才能ではありません。
経験と仕組みで、必ず鍛えることができます。
私自身、数え切れないほどの失敗を重ねてきました。
しかし、その一つ一つが、今の判断力の礎となっています。
ビジネスにおける判断は「人・数字・視点」で整える。
これが20年の経験から導き出した結論です。
明日から実践できることは、たくさんあります。
判断日記をつける。
小さな決断を意識的に行う。
選ばなかった選択肢を検証する。
あなたのビジネスにも、必ず活かせるはずです。
さあ、明日から小さな”選択”の精度を高めていきましょう。
最後に、ドラッカーの言葉を贈ります。
「最も重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを見つけることである」
判断に迷った時は、この原点に立ち返ってください。
きっと、進むべき道が見えてくるはずです。
参考文献
[1] 経営者の仕事 意思決定と判断は何が違うんですか?|トップマネジメント株式会社 [2] 経営哲学|京セラ – 稲盛和夫の経営哲学「京セラフィロソフィ」 [3] PDCAとは?目標達成を加速させるPDCAサイクルの回し方|古田土経営最終更新日 2025年12月4日 by iccimm